はじめまして、ちょっと変わった旅をする事が大好きなyuppi です。
このブログは、旅行好きな方やちょっと変わった旅をしたい方、旅行でどこにいこうか迷っている方などに向けて発信しています。
今回の記事は、沖縄(琉球)にある観音堂、琉球七観音についてまとめました。
沖縄本島北部から南部にかけて点在する七つの観音堂についてや観音堂の巡り方などについて紹介しています。
沖縄の琉球七観音について、少しでも興味を持って頂けると嬉しく思います。
よろしくお願いします。
この記事は、こんな方におすすめ
- 沖縄の観音堂について知りたい方。
- 沖縄の琉球七観音について初めて知った方や興味・関心がある方。
- 沖縄の琉球七観音の巡り方を知りたい方。
- 琉球七観音巡りを検討している方(メリット・デメリット)
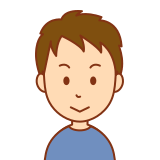
沖縄に観音堂ってあるのかな?

そう言われれば、確かにあまり聞いたことないよね!
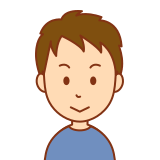
どんな観音堂があるのかな?
ちょっと、知りたくなってきたよ
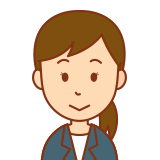
沖縄には観音堂ありますよ。
あまり知られていませんが、沖縄の琉球七観音を行くことをおすすめします。
沖縄のパワースポット沖縄七大御嶽(琉球開闢七御嶽)について知りたい方はこちらへ

沖縄の観音堂
観音信仰を中心とした霊場で、地域の人々の健康や子どもの成長を祈願する場として親しまれています。特に有名なのは「琉球七観音」と呼ばれる7つの観音堂で、それぞれが独自の歴史や特徴を持っています。
沖縄の琉球七観音
沖縄では観音信仰があり、各地に観音様の祠や観音堂が沖縄本島北部から南部にかけて点在する7つの観音堂です。
沖縄の観音信仰に基づき、家族の健康や子どもの成長、病気平癒などを祈願するために巡拝されます。
琉球七観音の歴史
琉球における観音信仰は、中国や日本から伝来した仏教の影響を受けています。特に、補陀洛渡海(観音浄土を目指す航海)や熊野信仰が琉球に伝わったことが背景にあり、琉球王国時代から近代に至るまで、沖縄独自の仏教信仰と民間信仰が融合しながら発展してきました。
明治維新後、日本本土からの宗教政策や神仏分離令の影響を受けましたが、沖縄では民間信仰として観音信仰が根強く残りました。
戦後も地域文化として再興され、現在では巡礼地として親しまれています。
琉球七観音は、沖縄独特の歴史的背景と民間信仰を反映した重要な文化遺産です。
主な特徴
病気平癒: 病弱な子どもの健康を祈願。
家族円満: 家庭の安全や繁栄を守る。
厄除け、受験祈願: 人生の節目における成功を祈る。
縁結び、夫婦和合: 家庭を築く縁を結ぶ。
- 〈琉球七観音〉
- 1. 奥武観音堂(南部奥武島)
- 2. 首里観音堂(那覇市首里)
- 3. 喜名観音堂(読谷村)
- 4. 嘉手刈観音堂(うるま市石川)
- 5. 金武観音寺(国頭郡金武町)
- 6. 久志観音堂(名護市久志集落)
- 7. 屋部寺(凌雲院)(名護市)
拝み方の基本
(1)門で合掌・一礼し、右足から境内へ入る。
(2)手水舎で手と口を清める。
(3)お線香やシルカビ(白紙)、お米などを供える。
(4)観音様の前で合掌し、声に出して住所・干支・感謝・祈願内容を伝える。
(5)お賽銭(クバンチン:三十五円)を入れる。
(6)左足から境内を出て、門で一礼する。
奥武観音堂(南部奥武島)
奥武島の観音堂(奥武観音堂)は、沖縄県南城市玉城地区奥武島の中央部に位置する歴史的な信仰の場で、琉球七観音の一つに数えられます。
奥武島は本島と橋で繋がっており、那覇空港から約21km(車で約40分)の場所にあります。
奥武観音堂の歴史
1600年代、唐(中国)の船が遭難して奥武島に漂着した際、島民が救助し手厚く介抱したお礼として琉球王朝を通じて黄金の観音像と仏具一式が贈られ、これを安置したのが始まりとされています。
沖縄戦で建物と黄金の観音像は失われましたが、戦後に再建され、現在は陶製の観音像が安置されています。
奥武観音堂は島民の深い信仰を集める場所であり、旧暦5月4日には航海安全や豊漁を祈願する「奥武島ハーリー」が行われます。また、5年に一度「観音堂祭」が開催され島民が感謝を捧げる伝統行事として受け継がれています。
| 場所 | 奥武観音堂(南部奥武島) |
| 住所 | 沖縄県南城市玉城奥武(MAP) |
| 営業時間 | 8:00〜19:00 |
首里観音堂(那覇市首里)
首里観音堂は那覇市首里にあり那覇空港から約8km(車で25分)の場所にあります。
首里観音堂は沖縄の観音信仰の聖地です。
沖縄で琉球七観音の中でも、首里観音堂は全国的にも有名です。
首里にある観音堂と言うことで「首里観音堂」の名で親しまれていますが、正式名称は「臨済宗慈眼院」です。
沖縄の琉球七観音としては、千手観音、薬師如来が祀られています。

首里観音堂(臨済宗慈眼院)の歴史
1618年、琉球王朝時代に尚久王が息子の無事な帰国を祈願して建立。以後、国王が国の安全や航海の無事を祈願する場として利用されています。
千手千眼観自在菩薩を祀り、すべての人を救済する大いなる慈悲を象徴しています。
また、首里観音堂は「首里十二支巡り」の一つ。干支の守り本尊が祀られていて御朱印集めの場として人気があり、初詣や坐禅会なども行われています。
境内からは那覇市内や港の絶景を楽しむことができ、観光スポットとしても人気です。
| 場所 | 首里観音堂(臨済宗慈眼院) |
| 住所 | 沖縄県那覇市首里山川町3丁目1(MAP) |
| 営業時間 | 9:00〜17:30 |
| 家内安全、健康祈願、病気回復、厄除開運、交通安全、安産祈願、商売繁盛、社運隆昌、心願成就 |
首里観音堂(臨済宗慈眼院)
喜名観音堂(読谷村)
喜名観音堂(きなかんのんどう)は、沖縄県読谷村喜名にある観音堂です。那覇空港から約30km(車で約50分)の場所にあります。
喜名公園内に、集落の氏神様「土帝君(トゥーティークン)」とともに祀られています。
喜名観音堂の歴史
喜名観音堂は、1841年に金武観音寺から千手観音を勧請して建立されました。それ以前は村民が金武観音寺まで参拝に行っていましたが、不便さを解消するために地元に観音堂を建てたとされています。
創建当初は瓦葺きの建物で、周囲にはリュウキュウマツが立ち並び厳かな雰囲気でしたが、老朽化により1964年にセメント造りへ改築されました。
喜納観音堂と並ぶ土帝君は、2012年に読谷村有形民俗文化財として指定されましたが、先の大戦により仏像は焼失してしまいました。
代わりに土帝君の祠にはビジュル(霊石)が祀られています。
無病息災や子孫繁栄を願う場として、村民の信仰を集めています。また、旧暦9月18日には観音堂祭が行われていて、地域との関係性の深い観音堂です。
| 場所 | 喜名観音堂 |
| 住所 | 沖縄県中頭郡読谷村喜名(MAP) |
嘉手刈観音堂(うるま市石川)
嘉手刈観音堂は、うるま市石川にある小さな祠で、歴史的な仏堂として市指定文化財に登録されています。
嘉手刈観音堂の歴史
地域の人々に親しまれる観音で、 1500年代、紀伊国(和歌山県)から金武に漂着した僧・日秀上人が、当時の伊波按司に進言して建立されたと伝えられています。
元は伊波城下にありましたが、2度の火災を経て現在の嘉手苅集落に移転しました。その後も幾度か被災し、1947年に再建されています。
「子育て観音様」として親しまれ、子育てや安産、子孫繁栄を祈願する参拝者が多く訪れます。旧暦1月7日には田芋を供えて村の繁栄を祈願する年頭行事が行われています。
また、地域の守護神として親しまれ、周辺には火の神「ヒヌカン」の祠や湧水「嘉手苅ガー」もあり、昔ながらの御願文化が色濃く残っています。
| 場所 | 嘉手刈観音堂 |
| 住所 | 沖縄県うるま市石川嘉手苅163(MAP) |
| 営業時間 | 24時間 |
金武観音寺(国頭郡金武町)
金武観音寺は、沖縄県金武町にある高野山真言宗の寺院です。
那覇空港から約約48km(車で約1時間10分)の場所にあります。
沖縄の琉球七観音の中でも首里観音堂と並び、全国的にも知られる観音堂です。
金武観音寺は聖観音菩薩を御本尊、脇侍に薬師如来と阿弥陀如来が祀られます。
金武観音寺の境内に鍾乳洞(日秀洞)があり、金武権現と水天が祀られています。洞内は自然美と信仰が融合した神聖な空間です。また、境内には樹齢約350年のフクギがあり、金武町指定文化財に指定されています。
沖縄では琉球七観音巡りの霊場、琉球王朝時代に特別に扱われた「琉球八社」の霊場として、拝まれています。

金武観音寺の歴史
16世紀に日秀上人が補陀落渡海の末に金武に漂着し、鍾乳洞を中心に仏教を広めたことが起源とされています。
創建した寺院で、現在の本堂は昭和17年(1942年)に再建されました。戦前の木造建築様式を残す貴重な建物として知られています。
昔ながらの木造建築に赤瓦屋根の寺院で庭園の亜熱帯植物など、日本と沖縄文化が調和した独特の雰囲気を感じることが出来ます。
| 場所 | 金武観音寺 |
| 住所 | 沖縄県国頭郡金武町金武222(MAP) |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |
久志観音堂(名護市久志集落)
久志観音堂は沖縄県名護市久志集落にある歴史的な観音堂で、琉球七観音の一つです。
那覇空港から約61km(車で約1時間30分)の場所にあります。
「ティラヌタンメー(寺のお爺さん)」とも親しまれ、地域文化と密接に結びついた場所です。
久志観音堂の歴史
1688年に設置され、昭和62年(1987年)に名護市の民俗文化財(有形)に指定されました。
琉球王府時代に「尚経」と「顧思敬」が観音像を受け取り、この地に安置したと伝えられています。
沖縄戦を乗り越えた唯一の観音像が祀られており、地域住民に深く信仰されています。
周囲にはガジュマルやアコウが生い茂り、独特の雰囲気を醸し出し、2023年には改修工事が行われ、新たな姿で地域住民や参拝者を迎えています。
子育て祈願、旅の安全祈願、受験生の合格祈願、さらに亡くなった人の魂を成仏させる「ヌジファー」など、多様な目的で参拝されています。
旧暦1月18日や9月18日には地域住民が健康や繁栄を祈願する行事が行われ、多くの参拝者が訪れます。
| 場所 | 久志観音堂 |
| 住所 | 沖縄県名護市久志(MAP) |
屋部寺(凌雲院)
屋部寺(やぶでら)は沖縄県名護市屋部にある寺院で、正式名称は「凌雲院」です。

那覇空港から約70km(車で約1時間50分)の場所にあります。
「琉球七観音」の1つに数えられ、本尊の薬師如来像を含む七体の仏像が納められています。病気回復や健康祈願にご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れるパワースポットです。
屋部寺は集落の氏神様「ウガンジュ(拝所)」として、「お寺のおじぃ(ティラヌタンメー)」と親しまれています。
屋部寺の歴史
1692年に凌雲和尚が創設。和尚は地域の発展や教育に尽力し、大旱魃の際には祈りで雨を降らせたとの伝説があります。
本尊の薬師如来像を含む七体の仏像が安置され、健康や延命などのご利益があるとされています。
「ヤブ医者」の語源とされていて、中国から来た無免許の名医が由来とされ、その医師が亡くなった後、屋部寺に祀られました。
観音信仰の一環として多くの参拝者が訪れます。
屋部寺は地元住民や観光客に親しまれ、特に健康面で不安を抱える人々におすすめの場所です。

| 場所 | 屋部寺(凌雲院) |
| 住所 | 沖縄県名護市屋部(MAP) |
おすすめの巡り方、モデルコース
那覇空港
↓約20km(車で約40分)
奥武観音堂
↓約15km(車で約40分)
首里観音堂
↓約17km(車で約50分)
喜名観音堂
↓約10km(車で約20分)
嘉手刈観音堂
↓約14km(車で約25分)
金武観音寺
↓約13km(車で約20分)
久志観音堂
↓約18km(車で約30分)
屋部寺(凌雲院)
・順番やスタート地点は自由ですが、南部(奥武観音堂)から北上するルートが効率的で、観光も兼ねて巡りやすいです。
・すべて巡らず、祈願内容やご利益に合わせて一部のみ参拝するのも良いです。
・各観音堂の特徴やご利益を事前に調べて、目的に合った場所を重点的に巡るのも良いです。
• お供え物や拝み方は沖縄独自の作法があるため、現地の案内や説明を参考にすると安心です。
• 旧暦9月や特別な祈願事がある時期に巡る家庭も多いのでその時期を避けることをおすすめします。
・各観音堂は住宅街や集落の中にあり、案内板が少ない場所もあるため、事前に地図やナビを活用するとスムーズに巡れます。
琉球七観音巡りのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| 健康祈願と病気平癒。 特に病弱な子どもの健康回復や家族全体の健康を祈願する場として適しています。 | 移動の負担。 琉球七観音は沖縄本島の北部から南部に広範囲に点在しており、移動距離が長くなるため、時間や体力が必要です。 |
| 家庭円満と縁結び。 家庭の平和や夫婦和合、良縁を願う人々にも人気があります。 | 天候や交通の影響。 沖縄の天候や公共交通機関の便が限られることがあり、計画通りに進まない可能性があります。 |
| 人生の節目の祈願。 厄年や受験、大きな祈願事がある際に巡拝することで、人生の節目を見守ってもらえるとされています。 | 準備の手間。 供物(お米やシルカビなど)を用意する必要があり、伝統的な作法を守るための知識も求められます。 |
| 精神的安定。 各観音堂で感じる厳かで優しい雰囲気が、心を落ち着かせ、リフレッシュさせてくれます。 | 混雑の可能性。 特定の日(例: 十八夜など)には参拝者が集中し、混雑することがあります。 |
| 地域文化の体験。 琉球観音信仰や沖縄独自の霊場巡りを通じて、地域文化や信仰に触れることができます。 |
これらの観音堂は、それぞれ独自の特徴や御利益を持ち、病弱な子どもの病気平癒や家内安全などの祈願事に適しています。また、龍神信仰と併せて拝むことでより良いとされています。
自分のペースや目的に合わせて、無理なく巡拝したり、家族や仲間と一緒に、沖縄の伝統文化を感じながら巡ることをおすすめします。
沖縄では1日で琉球七観音を巡拝する方もいますが、1ヶ月を掛けて数回に分け、巡拝する方もいます。
観音巡りは、家族や個人の幸福を願うだけでなく、心身の癒しにもつながる体験です。
まとめ
今回の記事は、沖縄(琉球)にある観音堂、琉球七観音についてまとめました。
とでる沖縄本島北部から南部にかけて点在する七つの観音堂についてや観音堂の巡り方、モデルコースなどについて紹介しました。
琉球七観音巡りは、沖縄独自の信仰文化を体感できる貴重な体験が出来ますので、少しでも興味を持って頂けると嬉しく思います。
よろしくお願いします。
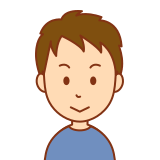
琉球七観音巡り!
初めて知ったよ。
とても興味深いですね。

